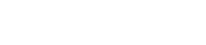タイムレコーダーで休憩時間や残業時間はどこまで記録できる?
従業員の勤務時間は始業時間と終業時間だけ記録すればいいというわけでなく、休憩時間や残業時間も必要不可欠な情報です。今回は、タイムレコーダーで休憩時間や残業時間はどこまで記録・管理できるのかを見てみましょう。
タイムレコーダーはあくまで時間を記録するツール
会社は、従業員の勤務状況(出勤、退勤、早退、遅刻、休憩、残業、欠勤など)を把握して、管理する必要があります。把握するためには、従業員に出社した時間や、退社した時間、休憩した時間を記録してもらい、それに基づいて判断することになるのですが、そのためのツールの1つがタイムレコーダー。
ここで大事なのが、タイムレコーダーはあくまでも、時間を記録するためにツールであり、勤怠を管理する仕組みではないということです。
タイムレコーダーによっては、設定に基づいて、休憩時間や残業時間を計算し、簡易的な集計をしてくれるタイプもありますが、複数の勤務体系に対応しているものは少ないので、すべての従業員に対応しきれないというケースも出てきます。
休憩時間や残業時間を管理する方法
では、異なる勤務体系や雇用形態に対応して、休憩時間や残業時間を管理するにはどうしたらいいかというと、
- 手作業で計算する
- エクセルで計算する
- 勤怠管理システムを利用する
の3つが主な方法です。(1)はタイムカードに打刻された時間や従業員が申告した勤務時間を元に、計算機をつかってひたすら手作業で計算するという形式で、管理する従業員の人数がごく小規模な場合に取られます。
従業員の人数がもう少し多い会社や店舗などでは、(2)のように、エクセルで出退勤時間を入力して、そこから休憩時間や残業時間を計算するという方法を取っているところも多いですね。
ただ、(1)、(2)ともに手作業による入力作業となるので、ヒューマンエラーが発生しやすく、時間がかかってしまうというデメリットがあるため、最近では中小企業でも(3)の勤怠管理システムを利用するという方法に移行する企業が多いです。
これからタイムレコーダーの導入を検討している場合は、その点を踏まえた上で、データをどのように集計し、管理するかというところも見据えて検討しましょう。
勤怠管理システムで休憩時間を管理する方法
では、勤怠管理システムで休憩時間を管理する場合、システムではどのように判断するのでしょうか?その方法には次の3つがあります。
1、従業員が登録する(打刻する)
休憩時間を従業員が自分で記録するという方法です。これは、勤怠管理システムの画面で、休憩開始時間と休憩終了時間を登録するという方法のほか、タイムレコーダーと勤怠管理システムがセットになっているタイプでは、打刻により登録するというものもあります。
2、時間帯設定
あらかじめ休憩開始時間と休憩終了時間を管理画面で設定しておくことで、その時間帯を含む勤務の場合は〇時~〇時までが休憩という登録を自動で行う方法です。
例えば、休憩時間の設定が12:00~13:00、17:30~18:00となっている場合、9:00~17:30まで勤務した場合は、12:00~13:00の1時間が休憩時間として、自動で登録されます。
自動で登録されるといっても、後から勤怠管理システムの画面で修正することが可能なシステムであれば、休憩の時間帯をずらした場合も変更が可能です。
3、勤務時間に応じた設定
勤務時間に応じた休憩時間を管理画面で設定しておくことで、勤務時間から休憩時間分を自動で減算するという方法です。6時間以上8時間未満なら45分、8時間以上なら60分を休憩とみなすという設定です。
フレックス制やシフト制を採用していて、従業員全てが同じ時間に休憩をとらないという場合に向いている方法です。
勤怠管理システムでの残業計算
残業時間は、会社の就業規則で決められた所定労働時間と法律で決められた法定労働時間に基づいて計算することになります。会社によって残業代の支払いについては違いがありますが、法定労働時間を超えて勤務した場合は割増賃金を支払う必要があります。また、深夜帯(22時~翌5時)の勤務には深夜手当の割増賃金が必要です。
これらの計算は、勤怠管理システムの管理画面で設定に応じて自動計算されるので、従業員は特に意識する必要はありません。また、勤怠管理システムでは残業時間の申請・承認機能を持つものが多く、事前、事後に関わらず上長による承認を通すことで不必要な残業を抑止する効果や、負荷の多い従業員を把握し、作業量を調整することで安全衛生対策につなげることも可能です。
労働基準法を守って適切な管理を
タイムレコーダーを導入すれば、休憩時間や残業時間をしっかり管理できると考える人も多いのですが、実際のところはタイムレコーダーで記録した勤務時間を計算するというワンクッションがあります。
コスト面を気にして、システム導入ではなく手作業やエクセルという選択肢をとる企業が多いのですが、自社で管理するには法令をしっかり理解し、その変更にも対応する人員が必要不可欠。その人件費はもちろん、給与をめぐるトラブルを避けるためにも、適切に勤怠を管理できる仕組みを選択するようにしましょう。